|
農業災害補償制度は、同様の危険にさらされている多数の農家が共済掛金を出し合って共同準備財産を造成しておき、災害があったときは、その共同準備財産をもって被災農家に共済金の支払いをするという農家の相互扶助を基本とした制度です。
平成22年12月現在の加入状況は、乳用牛等、肉用牛等、種豚および肉豚の合計で
250,112頭、補償金額8,246,655千円となっています。
 対象となる家畜は 対象となる家畜は
乳牛の雌等および肉用牛等(子牛胎児の加入が選択できます)は、新規(継続)加入時の月齢によっ
て次のように区分されます。
1)乳牛の雌等
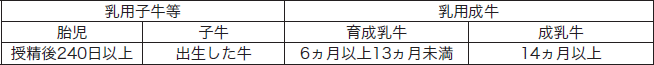
2)肉用牛等
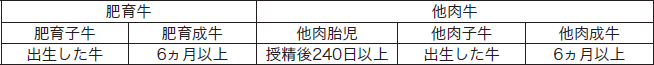
3)種豚
4)肉豚
|
・農家単位に、飼養している肉豚すべてが1年間で加入(包括加入)することになります。
・共済掛金期間開始後、出生した肉豚が出生後20日(出生後20日に離乳した日)に達した時は、
自動的に家畜共済に付されます。
|
 加入にあたっては 加入にあたっては
1)農家単位の全頭加入です。対象となる家畜は全て加入することとなります。
2)肉豚については、過去3年間において、自家生産豚が出荷のおおむね全頭を占め、その出荷先が
出荷資料の提供を得られる卸売市場等に出荷しており、今後もそれが確実な農家です。
さらに加入時には次の調査を行いますので、ご協力お願いします。
3)畜舎に立ち入り肉豚の頭数、母豚の頭数、畜舎の構造及び敷地面積等を調査します。
過去3年間の母豚の頭数、母豚ごとの分娩頭数、分娩回数、離乳頭数、離乳時までの死亡率
及び出荷頭数を聞き取りします。
 補償の内容は 補償の内容は
一定の資格を有する場合、死廃病傷のすべての事故については給付を必要としない場合は、それぞれ
自己経営の必要性に見合った給付を選択でき、掛金の割引により農家負担は軽減されます。
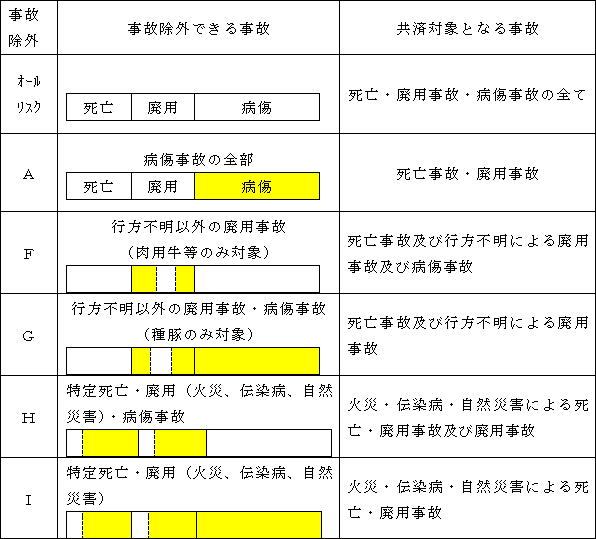
 掛金は 掛金は
1)1頭ごとの評価額を合計し「共済価額」を算出します。
2)20%(肉豚は40%)~ 80%の範囲内での補償割合(付保割合)を加入者が選択し「共済金額」を
算出します。
共済金額=共済価額×補償割合(付保割合)
3)共済金額に掛金率を乗じたものが「掛金」です。掛金の50%(種豚と肉豚は40%)を国が負担します。
農家負担掛金=共済金額×掛金率-国庫負担額
 異動が発生したら 異動が発生したら
1)加入者は、「異動記録簿」を作成する義務があります。
2)家畜の異動が発生した場合は、遅滞なく組合等へ通知しないと本来受け取れるはずの共済金が受け
取れなくなる場合があります。また、すでに支払われた共済金を返還することになります。
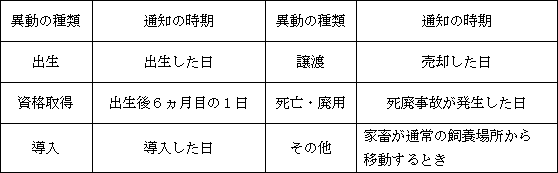
 事故のとき、共済金は 事故のとき、共済金は
1)病気になったときは
①速やかに獣医師の診療を受けてください。
②共済金の支払いは、病傷事故診断書について、以下の項目の内容確認が必要となりました。
・事故発生時の通知 ・診療内容の記録(3年間保存) ・診療費の領収書、振込証の写し
・共済金代理受領委任状(本人自署) ・手術痕確認
③疾病・障害等の診療費は、初診料を除いて一定の限度(病傷給付限度)まで共済金として支払われます。
2)死亡・廃用事故になったときは
①診療を依頼した獣医師を通じ速やかにNOSAIに連絡してください。
②共済金は共済事故発生時の付保割合(上限80%)を乗じて算出します。
③NOSAIの確認が必要です。同時に異動内容の確認も行いますのでご協力願います。
④廃用事故家畜については、写真撮影が義務付けられています。
⑤共済事故に該当した場合は、迅速な個体の搬出処理を行ってください。
⑥廃用事故の場合、売上伝票(仕切り書)、運搬料の領収書を提出してください。
⑦過去の被害率が一定水準を超える加入者に対して、共済金の支払限度が設けられています。
 損害防止のお願い 損害防止のお願い
損害防止をするために、農家が日常の飼養管理ですべき必要最低限の損害防防止
法律で義務付けられています。このような管理が出来ない場合は共済金が免責さ
れる場合があります。
|