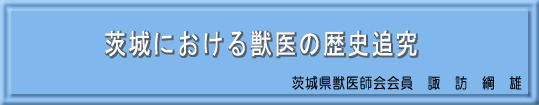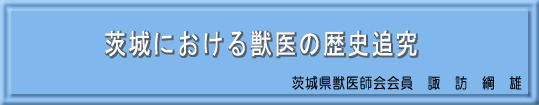古代の獣医技術
人間が原始的狩猟時代から抜け出し、古代時代に移行するとき従来、野山に生息する動物を身近に置いて遊牧の時代に移行することになる。そのため、次第に家畜化した動物の病気を治す原始的処置も必要とされるようになった。このことが現在の獣医技術に移行したものと考えられる。紀元前2500年頃には、既に家畜の骨折や助産行為が行われていたらしい。その事実は残された古代エジプトの壁画から、その一端を窺うことが出来る。しかし、わが国は古来島国であり農耕民族であったため、家畜の飼育も少なくそれに伴う家畜病気の治療技術も発展しなかったことは否めない。ただ453年頃に九州地方で書かれた『薩摩風土記』の中に馬の筋切断術が行われた記録が見られる。茨城においても『常陸風土記」が残されているが、馬に関する記録はあるものの、家畜の治療行為の記述は全く見られない。このことは、現存する『常陸風土記』は抄本であった為かもしれない。
茨城で出版された獣医学的古書
徳川家康の11男頼房公が慶長14年(1609)水戸藩の城主になり、水戸藩政が行われるようになってから歴代の藩主たちは、医学を始めとする学問や文化の向上、文教の振興を図ったとされる。特に2代藩主光圀公並びに9代藩主斉昭公は、積極的に医政に取り組んだことが知られている。特に幕末期において出現した藩医原南陽と本間棗軒等は、新しい蘭方医学取り入れて水戸藩の医学発展に大きく寄与した。また、これらの人々によって水戸藩では数多くの医書が発刊されている。その中から獣医的範囲と思われるものを紹介して見ることにする。
藩医原南陽著『 狗傷考』(天保7年1836)には、狂犬病発病論やその治療法、治療薬剤の投与方法、外科的治療法、鍼刺烙術、温灸術等細部に亘って記述されている。 狗傷考』(天保7年1836)には、狂犬病発病論やその治療法、治療薬剤の投与方法、外科的治療法、鍼刺烙術、温灸術等細部に亘って記述されている。
また、鼠毒による症状や解毒方法等が注目される。 同者著『戦陣奇方砦草』(文化8年1811)は、わが国での最初の軍陣医書として知られており、その内容は、戦陣における兵士の飲食衛生、蛇毒、野陣、馬病、船車酔い、防寒等45項目に渡って戦時における必要な軍事的医学知識が記述されている。
|
特に馬病については、遠乗り時の馬の扱い方や毒草摂取時及び貧血等の治療法等が克明に記述されている。また、藩医本間棗軒著『瘍科秘録(10巻)』(天保8年1837)は、外科を主とした各種の疾病が記述されている実用書として知られているが、本書の9巻に諸獣咬傷の項に、狂犬病に感染した犬の症状が克明に記され、更に現在人獣共通伝染病として問題視されている野兎病が、食兎中毒として取り上げられ、その詳細が記述されている。1914年に米国カリフォルニア地方において野兎病が発見される75年も前に本書に野兎病が取り上げられ論じられていたことに敬服するのみである。その他記録に残って書としては、真壁藩の水越佐中著『帝問馬師皇脈色論』(1856年)や古河藩馬医桑島良貞著『馬療法極』(1847年)等がある。
明治期における茨城の獣医事情
明治期に入ると明治新政府は、国力の増強と富国強兵の必要性のため畜産の振興と更に軍馬の需要上の施策が講ぜられることになった。茨城においても馬の改良と産馬奨励対策のため、明治10年馬貸付規則を定め、馬の衛生に関する条文も制定し、馬産の奨励に努めているが、当時は獣医師免許制度も無かったことからこの条文での医とは、馬医、伯楽等を指していたと推定される。明治14年に茨城県では、全国に先駆けて獣医鑑札制度を制定し、牛馬医の登録した者でなければ牛、馬の治療を禁ずる措置を執っている。しかし、獣医鑑札公布制度が出来ても、その当時の獣医は一般的にその技術が稚拙未熟であった。このことを憂いた那珂郡石崎村の笹沼剛氏が明治17年に当時の県知事に「獣医の改良は今日の急務也」との論説を提出したことが茨城勧業報告書に見られる。
明治18年8月に太政官布告により獣医師免許規則が制定され、この規則によって従来の獣医業務無免許自由の状態だったものが、免許証が無ければ、家畜の診療は許されないことになった。そのため、県では県内四箇所に獣医養成講習会場を設け、国から獣医学士を招請して巡回講習を開催している。
明治20年頃には獣医師開業試験が実施され、それによって県内に140名の獣医師が誕生することになった。そのため、県では獣医組合を組織し、獣医技術の改良、地方病の病原追及、伝染病の防疫更に家畜全般の健康衛生と保護を図る無目的で、獣医組合準則を定め県内獣医師の統合を図っている。
|