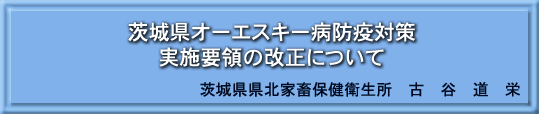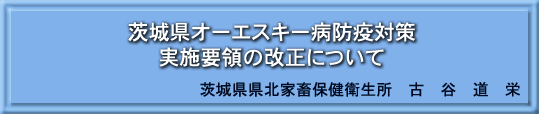オーエスキー病「以下、本病」は昭和56年に日本で初めて山形県にて発生し、その後関東、東北、南九州に拡大しました。昭和63年に最大の流行があり、発生頭数は約1万頭でした。その後、平成3年からオーエスキー病防疫対策要領によるワクチンを使用しての防疫体制になりました。この防疫体制は、全国への拡大防止には効果があるものの、常在化した地域に対する清浄化には期待された効果は上がっていませんでした。また、防疫対策開始より17年経過しており、国はその見直しをすることになり、オーエスキー病防疫対策要領を改正しました。これを受け本県では、平成20年7月17日に茨城県オーエスキー病防疫対策実施要領が改正されたのでその概要をお知らせします。
Ⅰ 基本方針
1 本病の清浄化を推進するためには、発症豚の淘汰だけでなく本病の感染源となる潜伏感染豚の早期更新が必要となる。
2 防疫対策は、モニタリング検査や清浄化段階に応じた抗体検査等により浸潤状況を把握しつつ、ワクチンを応用した野外抗体陽性豚の早期更新による清浄化を推進する。
3 ワクチンは、野外ウイルス抗体とワクチン抗体との識別が可能な同一種類のタイプのものを使用する。
4 防疫対策を的確かつ円滑に推進するため、県オーエスキー病防疫協議会、地域オーエスキー病防疫協議会(家畜保健衛生所単位)を設置する。
Ⅱ 農場における基本的な防疫措置
1 豚の所有者は、日常の飼養衛生管理の徹底(飼養衛生管理基準の遵守)に努める。
2 発生農場にあっては、発症豚の早期とう汰、野外抗体陽性豚の摘発・更新やオールインオールアウト等による豚群の計画的な更新等により清浄化を推進する。
3 本病の侵入を防止するため、抗体陰性豚の出荷、清浄地域からの豚の導入等を確実に実施する。このため、出荷豚のワクチン接種歴、導入元農場の清浄化段階等の情報提供を実施する。
Ⅲ 地域における清浄化対策
1 本病の浸潤状況を的確に把握するため、モニタリング検査(100戸 14頭以上)を実施する。
2 清浄化段階に応じた地域区分を設定(原則、市町村単位)し、地域一体となった防疫対応を推進する。なお、清浄化対策推進上、特に必要な場合には、豚の移動や地理的条件等の疫学的な関連を勘案した地域の設定が可能。
|
①清浄化対策準備段階(ステータスⅠ)
本病の有無を確認できない豚群がある。
地域内の飼養豚全頭へのワクチン接種が行われていない。
②清浄化対策強化段階(ステータスⅡ)
各農場において、統計学的に必要な頭数の抗体検査が行われている。
地域内の飼養豚全頭へのワクチン接種が行われている
③清浄化監視段階(ステータスⅢ)
本病の発生及び感染豚の摘発がない
ワクチンを応用した防疫措置を行っていない
④清浄段階(ステータスⅣ)
1年間、本病の発生及び感染豚の摘発がない
ワクチンを応用した防疫措置を行っていない
3 清浄化の段階を移行するために、各段階における統計学的に必要な検査頭数割合を設定した清浄度確認検査を実施する。この検査は、家畜保健衛生所のほか、民間獣医師や民間検査機関の活用を図り、効率的に実施する。
ステータスⅠからステータスⅡ 最大14頭
ステータスⅡからステータスⅢ 最大29頭
ステータスⅢからステータスⅣ 最大59頭
4 ワクチンを応用した清浄化の推進
(1)ワクチンの接種体制としては、市町村衛指協がワクチンを実施する。
なお、上記による接種が困難な場合は、地域防疫協議会が県防疫協議会へ別途協議する。
(2)ワクチン接種状況の把握として、畜産協会は、市町村衛指協からの接種記録簿等によりワクチン接種状況を地域防疫協議会へ報告する。
本病は海外の事例からも、清浄化可能な病気であり、現在の状況は清浄化まであと少しという状況にあります。清浄化のメリットは、単にワクチン接種の軽減のみでなく、清浄化の過程において、農場の衛生管理の強化が必要であり、そのことが他の慢性疾病の低減につながるものと考えられます。
また、本病の清浄化には、地域の養豚農家が一体となり、自分がワクチンを接種するのは自分のためだけでなく地域のためであり、隣の人がワクチンを接種するのは自分のためだけでなく地域のためであり、地域内の飼養豚全頭へのワクチン接種が必要です。
|