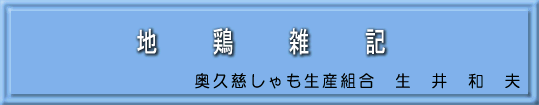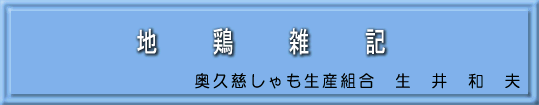今回は「奥久慈しゃも」と似た血統の地鶏と、雌系の親である名古屋種、ロードアイランドレッド種について書いてみます。
1.「伊予路しゃも」について
「奥久慈しゃも」血統は、父親が軍鶏、母親が名古屋種の雄とロードアイランドレッド種の雌との交雑種です。全国には多くの種類の地鶏が生産されていますが、これと同じ交配様式のものはありません。しかし、良く似た交配の鶏が四国におります。愛媛県の「伊予路しゃも」です。この鶏の父親は「奥久慈しゃも」と同じく軍鶏で、母親は雄のロードアイランドレッド種と雌の名古屋種との交雑種です。母親の両親の雄雌が逆になっているだけの違いです。「国産銘柄鶏ガイドブック 2007」で発育を見てみますと、平均飼育日数120日で、雄雌平均2.4となっています。「奥久慈しゃも」の140日で2.35と比べると、発育はやや良いようです。飼料は市販プロイラー用のものを使用していますので、食味第一に配合した専用飼料を使っている「奥久慈しゃも」よりも、発育が良いのでしょう。しかし、その差は小さくて生産性に大差なく、決して売り易い鶏ではありません。そのためでしょうか、生産羽数は上記ガイドブックによると、かなり少なくなっています。このようなことから、愛媛県ではより経済性に優れた「媛っこ地鶏」を作出しました。これは「伊予路しゃも」を母親とし、父親としては発育に優れ、ブロイラーの原種にも使用されているホワイトプリマスロック種を交配したものです。これによって発育は大幅に向上し、雄雌平均85日で2.8となっています。生産は二つの組織で行われ、生産羽数も大きく増加しました。これは販売が難しい高級地鶏から、販売し易い鶏を作り出し、その狙いが的中した面白い例だと思います。
なお、「奥久慈しゃも」は生産性が低く販売が難しくても、あくまでも味にこだわって行きます。
2.名古屋種について
名古屋種は元来、卵肉兼用種であり、多くの地鶏、銘柄鶏の原種として採用されています。また、この鶏は天然記念物ではないため、純粋の名古屋種が日本三大地鶏の一として販売されて、高級地鶏としての地位を確保しております。名古屋種はもともと、その名のとおり名古屋地方=愛知県で明治時代に作出されたものですが、地鶏として他県でも生産されています。関東地方では、群馬県で「名古屋コーチン」として、千葉県で「名古屋コーチン」の名称で生産、販売されています。兵庫県では「松風地どり」として、本場愛知県では五つもの生産組織で「純系名古屋コーチン」または「名古屋コーチン」として生産されています。
|
なお、本種は鶏としての正式名称は名古屋種であり、もともとはコーチン種を改良したもので名古屋コーチンと称していましたが、改良の過程でコーチン種の特徴である脚毛を除いた事等により、名古屋種となりました。
3.ロードアイランドレッド種について
ロードアイランドレッド種も元来卵肉兼用種なので、この種を雌系に使うと種卵の生産に有利であり、肉の味も優れているので、殆どと言ってもよいほど多くの地鶏や銘柄鶏に用いられております。そして、ロードアイランドレッド種の血液百分率75%の鶏が、上記ガイドブックに載っているだけでも6種類もあります。
地鶏と登録されているのは3種類、
地鶏瀬戸赤どり−香川県、25%はニューハンプシャー種
葵之地鶏−大阪府、25%はレッドコーニッシュ種(当初和歌山県で雛を生産したため、紀州徳川家の三つ葉葵の紋から名づけられた。)
丹波地どり−兵庫県、25%はニューハンプシャー種
銘柄鶏でも3種類、
純赤どり−青森県、25%はニューハンプシャー種
筑波茜鶏−茨城県、25%はニューハンプシャー種
三河赤鶏−愛知県、25%はニューハンプシャー種
「葵之地鶏」以外の各鶏種とも発育を良くするために、プロイラーの原種系の種鶏ニューハンプシャー種を25%配しています。「葵之地鶏」に使われているレッドコーニッシュ種は、発育がニューハンプシャー種、ホワイトコーニッシュ種或いはホワイトプリマスロック種などに劣りますが、肉味が優れるため、いくつかの地鶏の親に採用されています。
なお、血液百分率からは地鶏としての資格を持つ鶏を銘柄鶏としているのは、飼育日数或いは販売戦略上からと思われます。
また、この他にロードアイランドレッド種の血液百分率が50%の鶏も多く見られます。
これらからみてもロードアイランドレッド種の肉味の良さが、推察されます。
このように、「奥久慈しゃも」はどれを取っても肉質の優れた鶏種の組み合わせから成り、更に原種鶏プラスアルファの食味を持つ高級地鶏です。
|