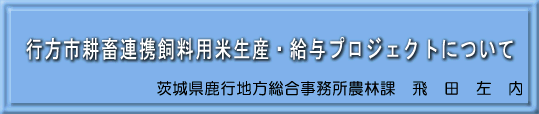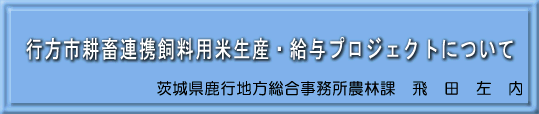はじめに
現在、配合飼料価格はバイオエタノール需要等により高騰し、畜産経営を圧迫しています。
一方、主食用米は生産過剰にあり生産調整が進められていますが、本県では湿田のため、麦や大豆などの転作作物が作付けできない圃場が数多くみられます。
このため耕畜連携による水田を利用した自給飼料生産や、水田放牧等の取組が行われてきており、特に稲発酵粗飼料(WCS)の作付けは拡大してきました。しかしWCSの生産には高価格の専用機等の導入や作業組織が必要など、すぐに取り組めるものでもありません。
そこで行方市において耕畜連携による既存の機械を利用した飼料用米生産の取組を進めている飼料用米生産給与プロジェクトを紹介します。
行方市耕畜連携飼料用米生産給与プロジェクトについて
行方市は湿田が多く米の生産調整の手段に苦慮してきました。飼料用米の取組なら湿田でも対応が可能で、水稲農家が持つ技術や既存の機械がそのまま利用でき、新たな設備投資が不要など、他の転作作物より容易に生産ができるのではないかと思われます。
さらに、飼料用米は畜産農家においても輸入にたよらない国内産飼料の利用拡大につながるものと思われます。
このような利点を生かすため、水稲農家と畜産農家を結びつけ地域内で飼料用米を生産・給与し、安全・安心な豚肉を生産するシステム構築による米の生産調整及び配合飼料の高騰対策に資する行方市耕畜連携飼料用米生産給与プロジェクトを立ち上げました。
プロジェクトの取組内容と進行状況について
今年度のプロジェクトの取組内容は、行方市内の作業受託組織(2組合)が飼料用稲専用種のクサホナミを53aの水田で栽培・収穫・乾燥を行います。田植えは5月23日、27日に行いました。クサホナミの生育については6月上旬頃まで気温が低温で経過したため、初期生育はやや遅れていましたが、7月以降の気温が平年以上であったため生育を取り戻しています。8月19日現在の生育状況は伸長期で、草丈は93cmになっており、10月中旬の刈り取りを予定しています。
今後の計画として、生産された飼料用米は市内の養豚農家に玄米で販売し、養豚農家は肥育豚の飼料に15%混合して2ヶ月間給与し、肉豚の発育調査や豚肉の肉質調査を行っていく予定です。なお、稲わらについては肉用牛に給与します。
|
推進体制について
行方市耕畜連携飼料用米生産給与プロジェクトを円滑に推進するため、関係各機関を構成員とするプロジェクト会議を設置して取り組んでいます。プロジェクト会議の構成員は飼料用米生産農家、養豚農家、肉用牛農家、行方市水田農業推進協議会、行方市、JAなめがた、関東農政局茨城農政事務所の他、県の地域農業改良普及センター、試験研究機関、総合事務所等で、各機関は飼料用米の生産管理技術や発育調査、生産調整に係る現地確認や交付金事務、飼料用米の流通システム、飼料用米の給与方法や発育調査、肉質調査等を役割分担して推進しています。
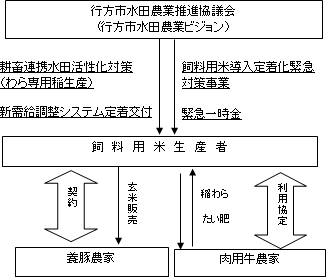
今後の課題について
クサホナミの栽培については今年度が初めてですが、現在までは既存機械の利用で順調に進んでいます。今後飼料用米の収穫以降の作業につきましても、既存の機械の利用性について検討していきます。
飼料用米を流通させるためには、飼料用米の販売価格が市販の配合飼料価格と同程度となることを考慮すると、飼料用米生産コストや流通コストの低減が課題となります。
さらに、飼料用米生産農家等のコスト低減の努力によっても補えない農家所得を確保する対策が必要です。
飼料用米の流通については、一般的には飼料メーカーを介した広域流通ですが、飼料用米生産給与プロジェクトでは生産農家から養豚農家への地域内利用を行い、生産履歴がわかる安全・安心な豚肉生産を目指しています。このため今後飼料用米の生産を拡大し、飼料用米を豚に通年給与していくためには、飼料用米の保管方法や運搬方法が課題となります。
おわりに
飼料用米の生産が拡大すれば輸入にたよらない自給飼料が生産され、飼料自給率向上に寄与するとともに、米の生産調整にも寄与できます。
また、米を豚に給与すると肉質がよくなるといわれており、地域の新たなおいしい安全・安心な銘柄豚の生産が期待されます。
|