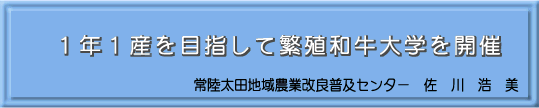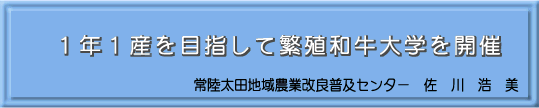多賀地域(北茨城市、高萩市、旧十王町)は、和牛の繁殖や肥育が基幹作目となっている地域です。繁殖農家は78戸で繁殖牛約500頭、肥育農家は28戸で肥育牛約5,000頭が飼われています。
BSE(牛海綿状脳症)が発生した平成13年以降、和牛は繁殖及び肥育ともに安定した好景気が続き、飼養者の高齢化等はあるものの後継者による規模拡大も着実に進んでいます。繁殖は子牛価格が高値安定するとともに、肥育においては全国枝肉共励会で毎年のように上位入賞を果たす飼養技術を持ち高い収益を上げてきました。
しかし、繁殖経営では表−1に示すように初産月齢が遅く、分娩間隔が長い、繁殖牛への過剰な飼料給与による過肥等の実態があり、高い子牛価格の陰に隠れる形で収益を低下させています。
表−1 多賀地域の繁殖牛の現状
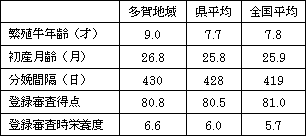
一方で、肥育経営においては子牛不足から価格が上昇し、優良肥育素牛の安定した確保が課題となっています。また、両方に共通する最近の飼料価格の高騰にも対処しなければなりません。
このため、普及センターではJA茨城ひたち繁殖牛部会と共催で、繁殖牛の1年1産と肥育経営への繁殖部門導入による一貫経営の育成を目標に繁殖和牛大学を平成19〜20年度の2年間開催することとしました。
開催に当たっては県の元気アップチャレンジ事業を活用し、関係機関の協力を得て実施しています。
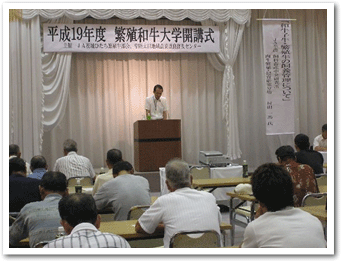
繁殖和牛大学開講式
|

繁殖牛・子牛の飼養管理講演会
課題である繁殖牛の1年1産を目指し、19年度は表−2に示すように飼養管理の基本技術の再確認のため、講義を中心に事例研修を交えて講座を開催しました。平均の参加者は約25名です。
講座の開催に当たっては一方通行にならないよう、実際に繁殖牛に給与している飼料を調べてもらい日本飼養標準に基づく飼料計算を行い、繁殖ステージにあわせた飼料給与について実例で検討し、給与飼料にメリハリが必要なことを納得してもらうような進め方をしています。また、最近変わってきた子牛の育成管理等、従来の考え方と変わった点については、「肥育農家に喜ばれる子牛」を強調して積極的に取り入れるよう提案しました。
12月には、肥育農家で繁殖部門の導入を検討している後継者5人で鹿児島県の曽於家畜市場と一貫経営農家の事例研修を行いました。
一般的な親牛からのほ乳、1週間で親子分離し人工ほ乳、ほ乳ロボットによる人工ほ乳を行っている農家の事例を研修することにより、それぞれの今後の経営構想に参考とすることが出来ました。また、実際に家畜市場から繁殖素牛の導入も行いました。
繁殖和牛大学の1年目も終わろうとしていますが、参加農家の皆さんの本格的な取り組みと結果が現れるのはこれからになるため、今後も規模拡大や自給飼料生産によるコスト低減、優良牛の確保対策等具体的な問題について身近な講座を目指して開催していく予定です。
|