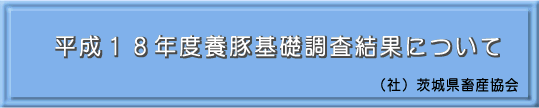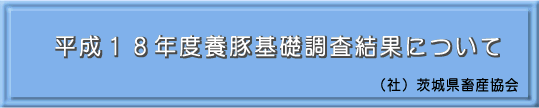社団法人日本養豚協会から県内の全養豚経営者について調査を委託されました。全国の調査については日本養豚協会から「養豚基礎調査全国集計結果(平成18年度)」が発表になっているので、今回は、茨城県内の結果について紹介します。調査基準日を平成18年8月1日現在として、経営状況や認定農業者、給与飼料(リサイクル飼料)などに関する事項を郵送により回答を得て集計しました。
1.調査結果の概要
本年度の調査対象経営戸数は、平成18年2月1日現在の全戸数613戸を対象に調査を行い、349戸(無記入を含む)で回答率は56.9%である。平均年齢は60.1歳、全国平均57.8歳と高齢化であった。
 2.養豚経営
2.養豚経営
養豚経営の労働形態は、家族経営87.9%、会社経営8.6%である。
前年比家族経営が2.4ポイント増(85.5%)、会社経営1.3ポイント減(9.9%)である。(全国集計では家族経営が増で会社経営が減である)
経営タイプは一貫経営74.6%、繁殖経営14.5%、肥育経営10.9%と前年と同傾向である。
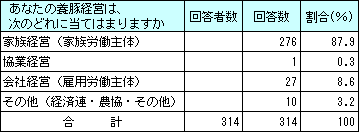 3.肉豚の出荷
3.肉豚の出荷
肉豚の出荷時日齢は平均188日齢、出荷時体重は112.9kg、枝肉重量は73.8kgで前年とほぼ同傾向である。
肉豚出荷状況については、出荷頭数が増加した16.9%、出荷頭数は変わらない41.9%、出荷頭数が減少41.2%で1/3以上の養豚生産者が前年より減少したと回答している。
肉豚の出荷頭数の減少要因をみると、①気象変動で生産性が低下した ②疾病の侵入で事故率が増加したが多くなっている。
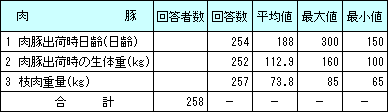
|
4.飼養頭数
種雌豚の全頭数は26,194頭で、そのうち純粋豚は1,551頭(5.9%)、種雄豚の全頭数は2,015頭で、そのうち純粋豚は1,904頭(94.5%)である。
種雌豚の品種割合は、交雑種94.1%でうちLW(78.1%)、WL(8.2%)と多く、純粋種のランドレース種(3.1%)、バークシャー種(1.0%)、大ヨークシャー種(0.9%)、デュロック種(0.7%)となっている。
種雄豚の品種別では、止め雄としてデュロックが88.8%(前年比0.6ポイント減)を占めている。
交雑種種雄豚では、海外ハイブリットが91.9%(前年87.6%)を占めている。
5.人工授精実施状況
交配方法は自然交配78.9%、自然交配と人工授精の併用19.9%(前年20.6%)、人工授精のみ1.1%(0.8%)となっている。
精液の入手方法については、全て自家生産が26.0%、全て外部導入が62.0%、併用が12.0%となっている。全国集計でも同様の傾向である。
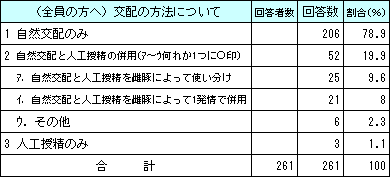 6.種雌豚の繁殖成績
6.種雌豚の繁殖成績
全体の1腹あたり平均哺乳開始頭数は、純粋種(L、W)10.3頭、交雑種(LW、WL)10.6頭、海外ハイブリッドは11.0頭である。
1腹当たり平均離乳頭数は、純粋種(L、W)9.0頭、交雑種(LW、WL)9.3頭、海外ハイブリッド9.6頭である。
平均育成率は、純粋種(L、W)88.4%、交雑種(LW、WL)87.7%、海外ハイブリッド88.1%である。
母豚の平均分娩回転率は、純粋豚(L、W)2.0回、交雑種(LW、WL)2.2回、海外ハイブリッド2.2回である。
7.事故率
離乳から出荷までの事故率は6.9%で前年比0.7ポイント良くなった。事故率の主な要因は呼吸器疾患が約80.3%を占めている。
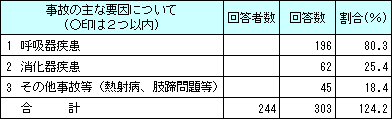
|