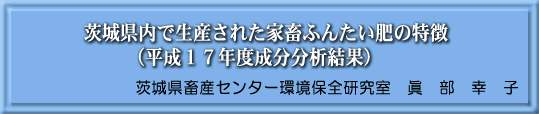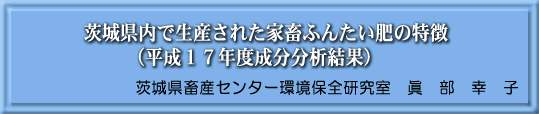たい肥化施設を導入するときに,どのような施設を導入したらよいか悩みませんか?
家畜ふんのたい肥化施設を区分すると,①たい肥舎,②開放型たい肥化施設(発酵層に攪拌機が付属したもの),③密閉型たい肥化施設(密閉された発酵層に撹拌機能や送風機能が付いたもの)の3つに区分できます。平成17年度に茨城県たい肥品質診断推進事業で茨城県畜産センターに搬入された家畜ふんたい肥の肥料成分の分析結果をもとに,処理方式ごとに生産されたたい肥の特徴を説明します(乳牛ふんたい肥54点,肉用牛ふんたい肥28点,豚ぷんたい肥58点)。
1 家畜ふんたい肥の肥料成分とC/N
家畜ふんたい肥の肥料特性は,水分・窒素・リン酸・カリおよびC/Nによって表されます。
C/Nとはたい肥成分中の炭素量を窒素量で割ったもので,土壌中で窒素がどの程度肥料として効くかを知る目安になります。
持続農業法(エコファーマー認定制度)を参考にすると,C/Nが10以上のものが「土づくりに関する技術」として活用できますが,C/Nが30を超えると窒素を肥料成分として期待できなくなるため土壌改良材とみなされます。
分析結果では,家畜ふんたい肥の88%がC/N10以上30未満であり「土づくりにもなるし,肥料としても効く」ことがわかりました。家畜ふんたい肥の利用を進めるためには,肥料成分の明確化(表示)が重要になります。なお,C/Nはオガクズ等水分調整材投入量が多いほど高くなり,発酵が進むほど低くなります。
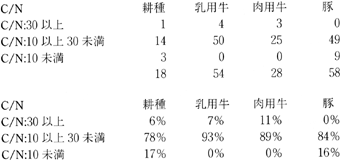
|
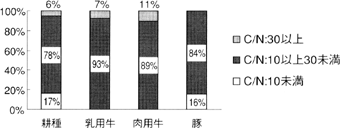 図1 家畜ふんたい肥および耕種農家たい肥のC/N
図1 家畜ふんたい肥および耕種農家たい肥のC/N
2 乳牛ふんたい肥の特徴と処理方式による違い
乳牛ふんたい肥は,C/Nが高く肥料成分が低いのが特徴です。たい肥舎および開放型たい肥化施設での処理が主流です。
(1)たい肥舎
水分が高く,水分率70%以上のものが2割ほどありました。ベタついてふん臭が残っているなど発酵不足であり,このようなたい肥は,水分調整材や切り返し作業を増やす必要があります。
(2)開放型たい肥化施設
他の方式に比べ水分が低く,カリが高いのが特徴です。
毎日1~数回の機械的な撹拌を行うことで,固まりの少ない均一なたい肥が生産できます。確実な切り返しによる発酵促進と高い水分蒸散能力から,たい肥の水分率が低くなります。ベタつかず,埃が立ちにくいなど取り扱いの容易なものになります。カリが高くなるのは,水分蒸散能力を期待した尿の混入や戻したい肥の多用・フリーストール牛舎の普及などが原因と考えられます。施設園芸などカリが過剰に蓄積した土壌には適さない場合もあります。
(3)密閉型たい肥化施設
C/Nが他の処理方式に比べ顕著に高くなります。処理施設への生ふん投入時に水分を低くする必要があり,多量の水分調整材を要するためC/Nが高くなります。発酵温度を維持するために鶏ふんや油粕を添加している事例もあります。
他の施設に比べ高額な設備投資が必要で,かつ水分調整材購入費が多額になるため,生ふんの水分率が高い乳用牛での導入には,十分な検討が必要です。
|