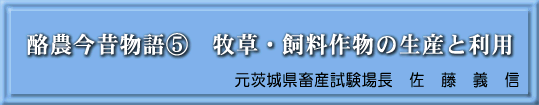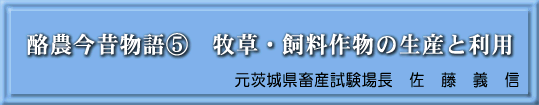1.牧草・飼料作の創始
わが国で最初に西欧式大規模農業牧場を開設した広沢安任は明治5年5月の開牧にあたり、圃場造成地と放牧地を区画し、開墾圃場には大小麦、ジャガイモ、それに本邦初のスエーデンかぶを栽培し、家畜は野草地に放牧した。
明治7年にいくつかの牧場にルーサン、エン麦、かぶなどの種子が輸入され、試作された。下総牧羊場(後の御料牧場)ではレッドトップ、チモシー、オーチャードグラス、ルーサン、レッドクローバー、ホワイトクローバーなどが栽培されたが、良好な結果は得られなかった。新山場長は欧米の牧場を視察後、明治33年に試験圃を設けて栽培法の研究を行い、成績も徐々に向上した。同牧場での適草種はクローバー類、チモシー、オーチャードグラス、ペレニアルライグラスなどであり、生草または乾草として利用し、併せてサイレージ調製についても試験し、成功を得た(御料牧場史)。
2.栽培試験と普及
本格的に栽培試験を実施したのは広島県の七塚原種畜牧場である。同牧場は明治33年3月に開設され、37年に各種の牧草・飼料作物を対象に適種選定および耕種法基準選定試験を行っている。
明治35年開設の茨城県種畜場においても七塚原種畜牧場に倣って栽培試験を開始している。これらの試験の結果、プレリーグラスの採種を行い、牧草種子配布規程を定めて普及を図った。
|
3.サイレージ調製
わが国で最初にサイロ(木製)を作ったのは神津牧場で、明治20年といわれている。上記の御料牧場では明治28年頃よりサイレージ調製試験を行い、良好な成績を得て30年代には場内生産物で家畜の飼料は自給自足状態にあったという。
結城郡上山川村の広江農場では大正年代に入って飼料生産も軌道にのり、飼養頭数も40頭と増えたため、大正4年に大谷石による地下8尺、地上13尺、内径15尺5寸、容量3,912立法尺のサイロ第1号基、数年後には地上10尺、内径14尺5寸、容量1,675立法尺の第2号基を建設した。しかし、これら本県初のサイロは昭和54年の道路拡張の際取り壊されて、現存していない。当時の牧草・飼料作物の栽培状況は下表のとおり。
期別飼料作物作付面積(昭和3年度)
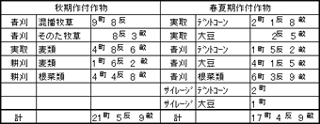
4.自給粗飼料の経営的意義
大家畜経営は牛がもつ反芻という生理的機能から、土―草―牛の有機的結合の上で合理的な技術の行使によって粗飼料の生産・利用を行い、経営の安定が確保されなければならない。酪農経営にあっては、牛乳生産費のなかで最も高い比率を占めるのは飼料費である(40.4%/H16、茨城県)。また、北海道よりも都府県で飼料費が高いのは、流通飼料費のなかに粗飼料の購入費が包含されているからである。
最後になりましたが、自給飼料作物の生産・利用を図り年間平衡給与体系を確保することは、乳牛の健康と乳成分の維持・向上そして経営費の低減に関与する課題であることを再認識し、生産性の高い経営を実践されるよう期待します。(了)
|