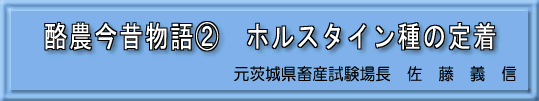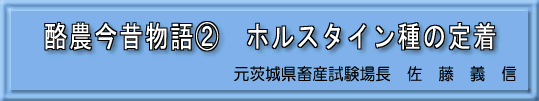1.乳牛品種の変遷
洋牛は明治元年から輸入されたが、このときの品種は不詳である。その後、明治20年代までの輸入総頭数は1,651頭で、その主体をなしたのは乳肉兼用種のショートホーン(約60%)、肉専用種のデボン(約30%)である。いま乳用牛の輸入と品種についてみると以下のとおりである。
1)ショートホーン種(短角種)
最初に輸入されたのは明治6年で、米国からである。その後、10年に米国から下総牧羊場(明治8年設立、同18年御料牧場となる)が牝15頭を輸入。当時の輸入目的は乳・肉兼用であったが、特に乳利用にあっては和牛の牝との交雑種が「搾乳用牛」として普及していった。
2)エアシャー種
最初に輸入されたのは明治11年で、札幌農学校に雄2頭、牝5頭導入されたが、外部普及は行われていない。19年に真駒内種畜場へ雄1頭、牝3頭、33年3月に七塚原種牛場が設置され、雄3頭、牝9頭が導入されている。その後、同種牛場は10年間で雄16頭、牝88頭を輸入し、増殖を図って貸付・払下げを行い、乳牛としての利用・普及に努めた。エアシャー種が何故に奨励・普及されたか記述がなく知る由もないが、本種は英国スコットランドのエーアー地方の原産で、同地方は砂礫が多くやせ地である。エアシャー種は体が小さく乳量は多くないが、丈夫で粗食に耐え、わが国の農家での飼育に適する牛、との判断によるものと思料される。
3)ホルスタイン種
最初に輸入されたのは明治22年で、米国から札幌農学校へ雄2頭、牝3頭、オランダから御料牧場へ雄2頭、牝8頭が導入された。このほか宇都宮牧場をはじめ北海道の民間牧場が米国、オランダから輸入している。このように、ホルスタイン種の飼養は明治末から大正時代にかけて普及されてきた。泌乳量が多かったことから小岩井、北海道の大規模牧場そして東京府下の搾乳業者において見直され、エアシャー種に替わってホルスタイン種およびその交雑種が大正年間に全国的に普及していった。
|
2.広江農場の牛飼養動向と乳量検定成績
1)牛の飼養動向
県内における飼養牛品種の動向を知る資料として、結城市矢畑の広江農場の「牛籍並交尾記録」がある。広江農場は50町歩余の規模で「無牛無農」を掲げ、耕種・養蚕・畜牛の三部門構成で戦後の農地解放に至るまで大規模農業経営を行っていた。牛の導入状況を年代順に示せば次のとおり。
| M |
28年6月 |
山内牧場からショートホーン雑種♂1、♀2 |
| |
38年5月 |
御料牧場からエアシャー♂1 |
| |
40年7月 |
茨城県種畜場からエアシャー♀1 |
| |
43年9月 |
七塚原種畜牧場からエアシャー♂1 |
| |
44年6月 |
月寒種畜牧場からエアシャー♂1 |
| |
45年5月 |
同上からエアシャー♀1 |
| T |
2年 |
石川牧場からエアシャー♀1 |
| |
2年10月 |
小岩井牧場からホルスタイン♀2 |
| |
4年 |
同上からエアシャー♀3 |
| |
4年10月 |
同上からホルスタイン♀2 |
| |
5年10月 |
同上からホルスタイン♀2 |
| |
10年7月 |
同上からホルスタイン♂1 |
| |
12年11月 |
町村牧場からホルスタイン♂1 |
| |
14年12月 |
同上からホルスタイン♀1 |
2)泌乳量の検定
広江農場がホルスタイン純粋種の農場に至るのには牛籍簿を作成して、牛個体の血統・繁殖・販売・死廃について明細な記録をとり、乳量検定を随時実施し、これらの成績に基づいた適正な淘汰を行い、優良牛の確保に努めたことによる。
下表に1日乳量検定の成績を示した。乳量のほかに比重と脂肪率についても測定しているが、個体泌乳量(泌乳能力)は低く、飼養管理の差を考慮しても今日の牛群検定成績とは隔世の感がある。
表 1日乳量検定成績
| 年/月 |
搾乳牛頭数 |
1日総搾乳量 |
1頭平均乳量* |
| M43/11 |
16(短角主体) |
6斗1升5合 |
7.144Kg |
| T3/10 |
15(短角+エアー) |
4斗7升3.5合 |
5.864Kg |
| S4/7 |
14(ホル種) |
25貫950匁 |
6.95Kg |
*1升=1.8リットル 1貫=3.75Kg、生乳の比重1.032で換算した。
|