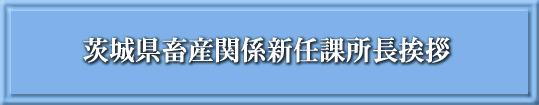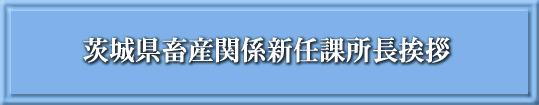この度の定期異動により、鹿行家畜保健衛生所勤務を命ぜられ過日着任いたしました。
県に奉職依頼、主として地方総合事務所と試験研究機関に勤務し、20年振りに家畜保健衛生所に戻りましたが、家畜衛生を取り巻く環境の変化に戸惑っているところです。
鹿行地域は周囲を鹿島灘と霞ヶ浦に囲まれた広大で平坦な土地を利用して、畑作中心の県下有数の農業地帯を形成しており、特に施設園芸が盛んでメロン、ピーマン、いちご等の銘柄産地の育成定着が進んでいます。また、土地利用型農業もかんしょ等を中心に盛んで、首都圏地域における生鮮農産物の供給基地として、今後さらに大きな発展が期待されております。
鹿行地域の畜産は首都圏の消費地に近いということと、飼料工場が鹿島港にあるという利点を背景に発展してきており、特に養豚は県内産出額の42%を占め、大規模飼養農家が多く、1戸当りの飼養頭数は1,580頭と県平均の約2倍という状況にあります。
|
畜産を取り巻く情勢は、畜産物などの流通の国際化が一層進展し、農家の経営規模がますます拡大しており、また、消費者からは安全・安心な畜産物の生産が求められ、家畜衛生対策事業の推進がますます重要となってきております。
中でも昨年1月に国内で79年振りに発生した高病原性鳥インフルエンザにつきましては、幸いにしてこの冬は未発生でありましたが、さらに監視体制を強化し、万が一の場合に円滑なまん延防止措置を講じることができるよう体制の整備に取り組んでまいります。
また、BSEにつきましては今年4月8日に国内で17頭目の発生があったところでありますが、引き続き県北家畜保健衛生所所管のBSE検査センターに職員を派遣し、24ヶ月以上の死亡牛の全党検査に協力してまいります。
最後に、当所は少人数ですが、気軽に来所いただけるような雰囲気づくりに努め、関係機関の方々のご要望に応えていけるように努力する所存でございますので、なお一層のご指導、ご協力をお願いいたします。
|