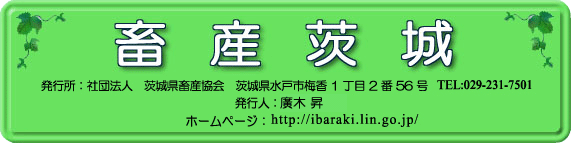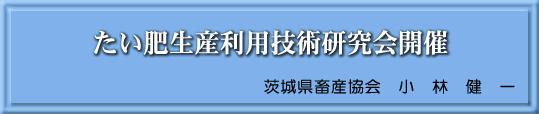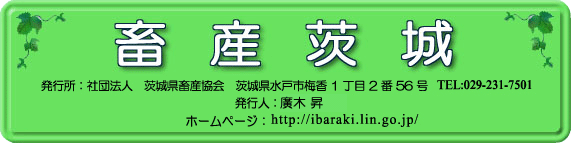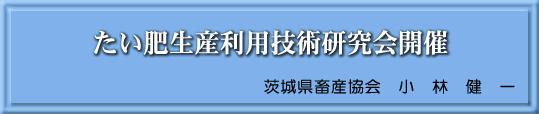去る2月2日、茨城町のJA全農いばらき農業機械センター研修室において(社)茨城県畜産協会、茨城県たい肥利用促進協議会による「たい肥生産利用技術研究会」を開催しました。たい肥の利用促進を図るために設立された本研究会も今年で3年目を迎え、当日は畜産農家、耕種農家、県、市町村、JA関係者など約120名が出席しました。
初めに「耕畜連携による土づくり」をテーマにたい肥利用側の横田卓士氏(龍ヶ崎市、水稲農家)及び平澤大臣氏(茨城町、野菜農家)、たい肥生産側の武熊俊明氏(八郷町、養豚農家)、行政側の渡邊稔氏(茨城県農林水産部農産課技佐)からそれぞれの取り組み事例が発表されました。
その後の意見交換会では、耕種農家から次のような意見や要望が出されました。
|
水稲農家:完熟たい肥を基肥として2t/10a入れているが、散布にかかる労働時間の軽減を図るため、窒素含有量を現在の倍にできないか。ナス農家:牛ふんたい肥を4t/10a使っており、後期の枝ぶりが良くなった。半熟たい肥は雑草が出て困る。品質の安定性や分析数値の表示などを通じて畜産農家は積極的にたい肥のPRをすべきである。ニラ農家
:乾燥圧縮たい肥を利用したいので、生産者を紹介してほしい。イチゴ農家:たい肥の品質が安定しないとイチゴの味にバラツキが出る。各地域でたい肥が安定的に供給できるよう市町村、JAに対したい肥センターの設置を要望したい。
最後に開いた(財)日本土壌協会専務理事の猪俣敏郎氏による講演「堆肥施用の現状と利用促進について」では、たい肥施用により収量とともに水稲は食味、野菜類はビタミンC、梨は糖度が向上するという調査結果が報告されました。
|