| 最新年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度〜 |
|
ホーム >
畜産茨城平成24年度 > 7月号 : 乳用育成牛における初産分娩月齢早期化に関する栄養学的研究 (平成23年度筑波大学学位論文(博士)) |
|
|
乳用育成牛における初産分娩月齢早期化に関する栄養学的研究 (平成23年度筑波大学学位論文(博士)) |
| 畜産センター 石井 貴茂 |
|
酪農経営にとって飼養管理の効率化は様々で
すが,後継牛の安定的な確保と効率的な育成
は,全ての経営に共通します。牛群検定におけ
る2008年の305日乳量は9,147kgで,約20年
前から約2,000kg増加しています。一方,育成
牛の管理目標である初産分娩月齢は,24ヵ月
齢を目標としていますが,現状は25〜26ヵ月
齢です。2000年以前は27ヵ月齢前後で推移し
ており,改善が図られない項目でした。初産分
娩月齢の遅延は,飼料費の上昇,後継牛の保有
頭数の増加,施設の利用効率の低下を招くため,
早期化することが重要です。
初産分娩月齢を早期化するためには,AI開 始適期が日本飼養標準で体重350kgとされて いるため,育成前期のエネルギー摂取量を増や すことにより,AI適期までの増体速度を高め る必要があります。しかし,育成期の高増体は, 乳腺や乳生産性に悪影響を及ぼすと海外の研究 者らにより報告されています。その一方で,日 増体量(DG)を1.0kgに高めても,飼料中 のCP含量を増加することにより,乳生産性に悪 影響を及ぼさないという報告もあります。また, エネルギーの増給により増体速度を高めた場 合,育成牛が太るのか?適正に発育するのか? といった点も明らかになっていません。 そこで,乳用育成牛の発育速度の限界を明ら かにするため,21ヵ月齢の初産分娩月齢を目 指した高増体育成が発育成績と初産乳生産性に 及ぼす影響について検証しました。
試験期間は生後90日齢からAI適期である
体重350kgまでの期間とし,試験区は目標DGお
よび給与飼料中のCP含量の違いにより3区
を設定しました。その内訳は,24ヵ月の
分娩を想定したDG0.75kg,日本飼養標準の標
準的なCP水準である14%のMM区(標準増
体・標準CP区),21ヵ月齢の分娩を想定した
DG1.00kg,CP14%のHM区(高増体・標
準CP区),そしてDG1.00kgでCP水準を16%に
高めたHH区(高増体・高CP区)です。
表1に発育成績と飼料摂取量の結果を示しま した。350kg到達日齢は高増体区のHM区 とHH区が,標準増体区のMM区に比べ約40日 間早まりました。実際のDGはMM区が0.97kg,HM区とHH区が1.1kg前後でした。 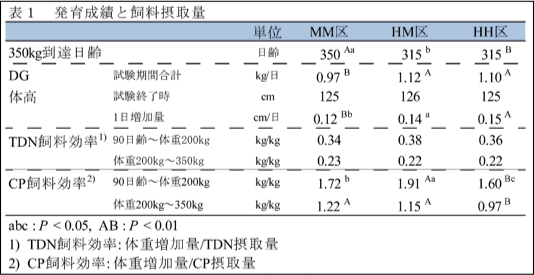
それぞれの区で目標DGを上回りましたが,これは,日
本飼養標準(1999)は,育成牛のエネルギー要
求量の算出において,MEの正味利用効率が季
節によって影響を受けるため,7%の安全率を
見込んで設定されています。そのため,エネ
ルギーが過剰になったためと考えられます。ま
た,DG0.97kgとDG1.1kgで発育させた牛の体
格に差がなく,体重350kgまでの発育速度
をDG1.1kgまで高めても,DG0.97kgと同程度な
発育であることが明らかになりました。
さらに,DG1.1kgで発育させた場合,CP水準の違いで
は350kg到達時の体格に差が認められず,CPの
増給は体格に影響しないことが明らかになり
ました。また,表1のCP飼料効率の結果
からCP16%はCP摂取量1kg当たりの体重増加量
が14%に比べ少なくなりました。図1の血中尿素
態窒素(BUN)濃度はCPが過剰であると高値
となりますが,HH区で試験期間を通じて高く
推移しました。これらのことから,DG1.1kgに
おけるCP水準は14%程度で飼養するのが適正
であると推察されました。
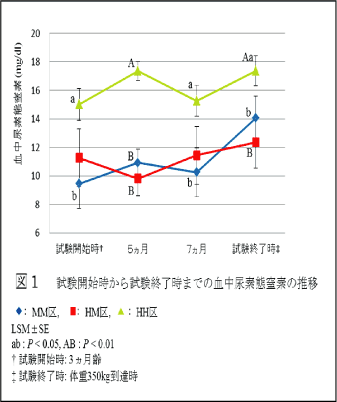
表2に分娩成績および泌乳成績を示しまし
た。HM区とHH区は21〜22ヵ月齢で初産
分娩を迎えました。また,MM区と分娩難易
度に差がなかったことから,初産分娩月齢
を21ヵ月齢に早めても正常な分娩が可能であること
が示唆されました。305日乳量に関して
は,HM区とHH区がMM区に比べ1,500〜2,500kg低く
なりました。また,飼料中のCP含量を高
めても,乳量が低下しました。これらのことか
ら,乳量を減少させずに21ヵ月齢で初産分娩
を迎えるためには,AI適期までの発育速度
をDG0.97kg以下,CPを14%程度で飼養するの
が適正であると推察されました。
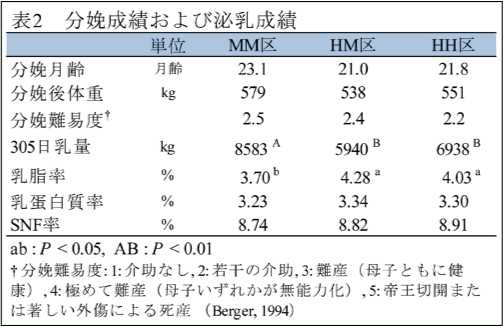
これまでの結果から,初産分娩月齢の早期
化において,育成期の増体速度と乳生産性の関
係について一定の結論を得られましたが,乳生
産に最も影響を及ぼす要因が,育成期の増体速
度・分娩月齢・分娩時の体重・その他の要因な
のかが明らかになっていません。また,前記
の試験成績を精査するためには,一般管理の乳
牛と比較して評価する必要があります。そのた
め,試験牛のデータに加え,一般管理の育成牛
のデータを合わせた計116頭のデータで,乳生
産性に影響を及ぼす育成管理要因について解析
と考察を行いました。その結果,乳量と乳成分
量へ強く影響を与える要因は,受胎時の体重で
した。また,受胎時の体重が1kg増加すると,
乳量が8kg程度増加するということが示され
ました。育成期の増体速度も乳量に影響を与え
ることが明らかになりました。また,MM区
の305日乳量は一般管理牛と同等であったこと
から,DG0.97kgまでは乳生産性に影響を及ぼ
さないことが明らかになりました。日本飼養標
準(2007)では,AI適期までの発育速度の限
界は明らかにされていないため,DG0.95kg程
度に留めることが安全とされていますが,本
解析から0.97kgまでは安全であることが示さ
れました。また,高増体区の解析結果
から,DG1.03kgを超えると乳量は減少するという結
果も示されました。
以上の結果を応用し,「21ヵ月齢の初産分娩
における乳生産性を高めるための発育曲線」を
図2に示しました。この発育曲線は21ヵ月齢
の初産分娩を前提とし,乳量が減少しない増体
速度と最大の受胎時体重を両立しています。ま
た,MM区,HM区,HH区の分娩難易が,難
産を示す3以下のスコアであったことから,そ
れらの分娩時体重を目標とした安全を考慮した
発育曲線です。

この発育曲線の具体的な効果ですが,1つめ
は受胎時体重が1kg増加する毎に305日乳量
が8kg程度増加するという結論から,体重350kgに
比べ375kgの受胎は,初産乳量が200kg増
加することが期待できます。
2つめは飼料費の減少が上げられます。大 まかな試算の結果ですが,375kgでの受胎を 前提にすると,DG0.62で現状の26ヵ月分娩 (DG0.62kg)の場合は,飼料費が284千円で, 粗利益(乳代−飼料費)は365千円です。同 様に24ヵ月分娩(DG0.75kg)の場合は,飼料 費が265千円で粗利益が383千円。図2の発育 曲線(DG0.97kg)では,飼料費は257千円で, 粗利益が391千円となるため,26ヵ月齢に比 べ26千円。24ヵ月齢に比べ8千円の利益の向 上が図られます。 3つめは安全に初産分娩が迎えられる。これ は,前述したとおり分娩事故の危険が少ない体 重まで増体させるためです。 4つめは保有頭数の減少。平均産次2.7産, 経産牛頭数40頭,子牛損耗率5%の経営の場合, 初産分娩月齢が26ヵ月の場合の育成牛保有頭 数は30.5頭です。しかし,同じ条件で24ヵ月 齢に短縮された場合は28.1頭,さらに21ヵ月 になった場合は24.6頭と約6頭少なくなります。
日本国内では,今回のような100頭を超える
乳牛のデータを用いて解析した研究は,今まで
行われていません。さらに,本研究では近年の
能力向上が図られた乳牛の初産泌乳期の305日
間の実乳量のデータを用いているため,現在の
酪農の実情に即していると考えられます。本研
究によりDG0.97kgまでは初産305日乳量に影
響せず安全であることが明らかになりました
が,これは社団法人日本ホルスタイン登録協会
における標準発育値の上限を超えている
ため,AI適期までの増体速度を再検討するきっかけ
になるデータといえます。また,日本飼養標準
(2007)におけるAIの開始基準は,体重
が350kgで体高が125cmとされていますが,これは
基準に達しない受胎は分娩事故あるいは分娩後
の乳生産性の低下を招くというマイナス面から
設定されている基準です。今後は,その基準に
加え初産時の乳生産性を高めるために受胎の目
標体重を設定することを提案していく必要があ
ると考えられます。
|

|