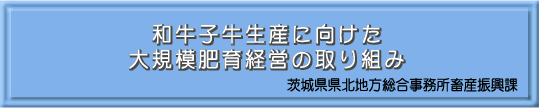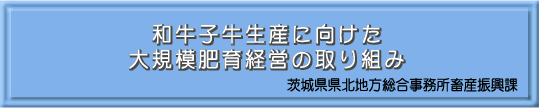「常陸牛」は、生産者と関係機関の努力により市場での評価も高まり、出荷頭数、販売店数とも順調に増加してきました。しかし、肥育素牛は栃木、福島など隣接県をはじめ、鹿児島、宮崎、北海道を中心に県外導入が大半を占めており、茨城県産による自給率は10%程度にとどまっています。
子牛生産は全国的にみると九州、北海道を中心に増頭に転じていますが、市場における需給のひっ迫傾向は続いており、子牛価格は平成18年度と同程度の高い水準で推移しています。このことは肥育経営にとっては、飼料価格の高騰とともに所得を確保していくうえで大きな課題となっていますことから、大規模肥育経営が繁殖部門に取り組み始めた事例を紹介します。
経営の概要
・経営形態 交雑種肥育経営
・会社設立 平成12年6月有限会社設立
・飼養規模 交雑種肥育牛 常時2,000頭
繁殖雌牛 80頭
・出荷頭数 交雑種肥育牛 年間1,000頭
・従業員 15名

代表取締役 島崎尋栄氏
有限会社和洋茨城牧場は、平成12年度に埼玉県から常陸大宮市に移転してから8年目となる大規模肥育経営体です。交雑種肥育を中心に、早くより哺乳ロボットを導入するなど、省力的な飼養管理を目指した経営を行っています。交雑種肥育が主体ですが、規模拡大を進めていくなかで、和牛肥育を本格的に開始する構想があり、子牛供給に対する不安が繁殖部門の導入を決断するきっかけとなったそうです。

カーフペン |

哺乳ロボット
繁殖用雌牛は既存牛舎を活用し平成18年に育成牛を90頭導入、人工授精を行った結果、初年度の平均種付回数が1.3回と良好で、80頭の子牛生産がありました。
群馬県の酪農部門で行っている方式による超早期離乳を行った最初の子牛群で事故が多発するなど、失敗もありましたが、子牛を分娩後1週間で離乳、カーフペンによる個別管理を10日間行うなど独自に改善した結果、現在は順調に育成が進み、子牛の一部はすでに肥育が始まっています。繁殖雌牛は全頭群管理で、人工授精を含めた繁殖管理は、繁殖部門の開始に併せて雇用した職員一人が行っています。
繁殖部門は今後、食肉市場や子牛市場の動向などを見極めながら5〜10年をかけて成牛常時飼養600頭まで規模拡大する構想を持っているそうです。和牛肥育部門については、外部導入は当面せず、子牛生産を主体とし、自家生産子牛の増頭に併せて規模拡大していく考えです。
一般的に一貫経営への転換は、自家生産による子牛の安定確保と、育成から肥育過程へロスのないスムーズな飼養管理の移行ができること、また長期的には経営内改良により、肉質の向上や均一化ができるなど、メリットがある反面、生産期間の長期化による資本回転率の低下、施設などへの追加投資や、飼料費などに要する資金の調達と、元利償還による収益の圧迫などの問題が生じやすく、技術の習熟も大きな課題となります。
和洋茨城牧場の場合、交雑種肥育を経営の柱として安定した所得を確保しながら、自己資金の範囲内で規模拡大を進めてきたことによる資産的な裏付けが、リスクを伴う経営展開を可能にしている要素だと考えられます。規模拡大していくにあたっては、島崎氏も話されておりましたが、繁殖・哺育育成・肥育の各段階で、技術に習熟した人材を養成し確保していくことが重要だということです。
繁殖部門の導入により一貫経営の有利性が発揮されるのはまだ先であり、生産コストの大幅上昇など厳しい情勢のなか、規模拡大をすすめるには判断が難しい状況ですが、将来を見据えた茨城和洋牧場の取り組みは、一貫経営化のモデルとして地域肉用牛生産の活性化と、常陸牛の生産拡大につながるものとして関係機関として大きく期待しています。
|