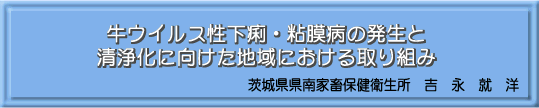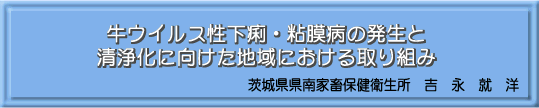管内ある酪農地域において,牛ウイルス性下痢・粘膜病による流産が発生したことを受けて,地域酪農家,酪農組合獣医師,市役所と協力して地域ぐるみで清浄化の取り組みを行ったのでその概要を紹介します。
病態
牛ウイルス性下痢・粘膜病に感染すると,発熱や呼吸器,消化器症状,免疫抑制状態などが認められますが,一般には軽度な症状で回復するか,不顕性感染で終わることが多いようです。問題は,妊娠初期の母牛に感染すると,胎仔は免疫寛容状態となり,持続感染牛として生まれ,生涯ウイルスを出し続けて,農場内の汚染源となってしまう点です。
発生経過
A酪農家で平成19年3月,流産が発生し,この流産胎仔(写真1)を病性鑑定した結果,牛ウイルス性下痢・粘膜病(以下,BVD-MD)による流産と診断しました。A酪農家内に持続感染牛が存在し感染源となっている可能性があるため,汚染状況の調査及び持続感染牛を摘発する目的で農場内全頭の血液検査を行いましたが,持続感染牛は摘発されませんでした。これにより,農場外部からのウイルス侵入の可能性を考え,同じ酪農地域全体の汚染状況を調査するために,地域酪農家全7農場を対象としてBVD-MDに関するアンケート調査を行いました。その結果,流産の発生や,虚弱仔牛の娩出が地域全体で起こっていることが分かりました。そこで搾乳牛の中にウイルスを排出しているものがいるかを調べるため,バルク乳検査を行いました。検査の結果,B酪農家1戸で,バルク乳検査陽性となりました。

写真1 A酪農家流産胎子
|
この結果を受けウイルス排出牛を特定するため,B酪農家内全頭の血液検査を行ったところ,3頭の持続感染牛を摘発しました。
その後の検査によりA酪農家と,B酪農家で分離されたウイルスの細胞病原性及び,遺伝子型はすべて一致したことから,今回のA農場の流産は,B農場が感染源となっている可能性があると考えられました(図1)。
清浄化対策検討会
一連の発生を地域全体の問題として考え,地域酪農家・酪農組合獣医師・管轄市役所・家畜保健衛生所で清浄化対策について検討会を開きました。病気の概要を説明し,一連の検査によりB酪農家で持続感染牛が摘発された経緯を説明しました。また,農場内に大量のウイルスを出し続ける持続感染牛の摘発・とう汰を全農場で継続して実施していく必要がある旨を指導し,さらに同じ時期にワクチンの一斉接種をすることで,地域全体でBVD-MDに対する免疫力を高めることを指導しました。
今後
当該酪農地域の清浄化を達成するために,A・B酪農家以外についても,バルク乳検査を定期的に行うと同時に,搾乳牛以外の牛の血液検査を実施し,摘発された持続感染牛を早急にとう汰することで,清浄化に向けた取り組みを継続していく予定です。
課題
持続感染牛のとう汰に見合う損害補填体制を整えることやワクチン接種に対する経済的な補助がBVD-MDの清浄化に必要であると考えます。
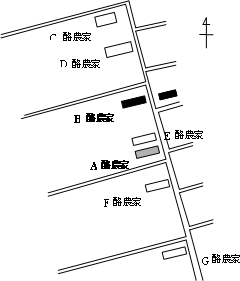
図1 酪農地帯 牛舎見取り図
|