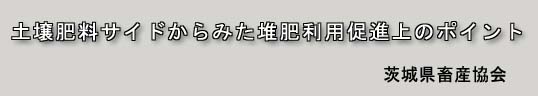
平成15年5月23日に茨城県畜産センターに於いて行われた第46回茨城県畜産研究会発表会(シンポジウム)で「土壌肥料サイドからみた堆肥利用推進上のポイント」と題して茨城県農業総合センターの武井昌秀氏から発表を頂いた中から「土づくりの目的(土壌の肥沃土・堆肥施用効果)と堆肥の製造・流通」に係る部分について概要を紹介します。 しかし、このような情勢でも、農家段階では必ずしも堆肥を積極的に導入する機運が高まっているとは言い難い。 ①取り扱い方が難しい ②施用効果が必ずしも実感出来ない等の理由から、敬遠する向きもある中で、土壌肥料サイドからみた堆肥利用について発表を頂いた。 1 土壌の肥沃土を考える 堆肥を投入して土づくりをする目的は、土壌の窒素肥沃土を高めることであろう。土壌の窒素肥沃土を水稲を例に考えた場合、生育期間中に水稲は、窒素を10〜12kg/10a程度吸収する。このうち、施肥由来窒素が占める割合は、土壌条件によって異なるが、40%程度である。残りの6kg/10a程度は土から供給された窒素である。この窒素は、土壌に含まれる有機物が分解して放出されたものであり、その供給源を可給態窒素(いわゆる地力窒素)という。可給態窒素は有機体の窒素であり、これが分解して無機態窒素に変化するのである。 2 窒素肥沃土の変動について 砂質の沖積土水田を例とした場合、毎年6kg/10a程度の土壌由来窒素(土壌窒素)を吸収する。土壌条件によって異なるが、土壌中には20kg〜90kg/10a程度の可給態窒素が存在すると考えられ毎年水稲作付け期間中に土壌から5kg〜10kg/10a程度の窒素が供給されている。 可給態窒素とは、植物には直接利用されないが、微生物の働きで植物に利用される形態に変化できる有機性の窒素で、いわゆる地力窒素である。 通常水田では、①施肥した窒素の一部が有機化して地力窒素となる。②作物残渣の窒素は徴生物に取り込まれて地力窒素となる。③ある種の微生物によって空中窒素が固定されて地力窒素となる。等によって、毎年窒素がほ場に還元されている。 この窒素が翌年土壌から土壌窒素として供給されている。よって、水田では堆肥等を施用しなくても土壌の窒素肥沃土はある程度維持される。しかし、そのことは水田に堆肥を施用しなくても良いということではない。水田への堆肥の連用によって土壌の窒素肥沃土は確実に増加する。 畑や樹園等の場合は水田と異なり土壌が酸化的であり、乾湿が繰り返される条件にあるため、土壌中の微生物の活動や種類が大きく異なっている。微生物による分解能は大きく、水田の微生物層がほとんど細菌で占められているのに対して、畑や樹園地では糸状菌が優勢である。 また、土壌の乾湿が繰り返される条件下では、いわゆる乾土効果によって土壌窒素の無機化が促進され地力窒素の消耗が大きい。水田を畑地化した場合、土壌の窒素肥沃土は低下する。そのため、畑の窒素肥沃土を維持するためには堆肥の施用が必須である。 3 堆肥の品質と施用効果 C/N比は、無機態窒素を放出するか固定するかの分かれ目を示す。堆肥も土壌と同じように乾燥すると乾土効果と同じ現象が見られ、水分によって窒素の無機化速度が大きく異なる。また、副資材によっては、はじめから無機態窒素を含むものもあり、この場合、窒素は、化学肥料と同じ肥効を示す。 ・C/N比が低く、無機態窒素を含み、水分が少ない堆肥は肥料的効果(即効性)が高い。 ・無機態窒素が無くて水分が高く、C/N比が30以下の堆肥は、地力的効果(緩効性)が有る。 ・C/N比が30以上の堆肥は施用した年にはほとんど窒素の肥効が認められない、遅効性である。 |
・窒素の肥効が期待できないC/N比が30以上の堆肥でも、次の効果が期待できる。 堆肥の施用年の肥効は少ない。 施用した堆肥は.土壌バイオマスの増大(地力窒素の増加)に頁献する。 土壌バイオマスの増大は、翌年以降の土壌窒素無機化量の増加につながる。 すなわち、堆肥の施用効果は施用した年でなく、翌年以降に現れる。よつて、堆肥は連用することが大切である。 4 堆肥に含まれるその他の養分の肥効について 窒素以外の作物に必要な成分のリン酸等にも無機態と有機態が存在する。堆肥に含まれる窒素以外の有機態養分も有機物の分解に伴って徐々に可給化するので、基本的には化学肥料と同様に扱えると考えて良い。特に、堆肥を連用しているほ場では過去の蓄積を含め、投入した成分量がそのまま肥効につながると考えて良く、それらの養分の適正施用量は化学肥料と同じにすべきてある。 ・無機のリン酸等の肥効は、化学肥料とほぼ同等である。 ・有機態成分は、有機物の分解に伴って有効化する。 ・堆肥に含まれる成分は、表示量で示された量で化学肥料と同様に扱う必要がある。 ・堆肥に含まれる成分が、過剰施用にならないように配慮しなければならない。 ・適正施用量 ≒ 持ち出し量 5 堆肥使用時の留意点 ・堆肥の品質を熟知する。 ・目的にあった堆肥を選択する。 ・成分表示に基づいて、適正施用する。 ・連用により、施用効果が安定する。 ・畑や樹園地への堆肥施用は必須である。 堆肥を自らの目的にあわせて選択し、土壌診断や作物の生育目標に合わせた適正施用量を考慮して使用することが大切である。 6 堆肥の製造及び流通に求めるもの 「肥料取締法の一部改正に関する法律」により、品質表示が義務付けられた。堆肥の品質表示がなされることは、使用者にとっては使いやすくなる等のメリットも大きい。しかし、堆肥製造では堆肥の原料や製造条件の変動等によってその品質が変化する可能性があり、製品の貯蔵段階でも品質の変化が起こり得る。 堆肥はその品質によって施用効果が異なることから、使用者にとっては、常に一定の品質で、成分表示が信頼できることが重要である。表示義務はないが、堆肥の肥効特性(速効性、緩効性等)や使用例(直播き水稲用とか使用できる機械等)が示されていると使用者には使いやすいし、商品としての差別化につながる。 また、成分バランスが大きく異なる製品を使用する場合、多く含まれる成分の過剰(カリ、銅、亜鉛等の重金属)施用、投入量が制限されるなどの問題が発生するので堆肥の品質向上と均質化が必要である。 また、堆肥の施用が良いとは分かっていても、成分濃度が低く、大量に施用しなければならないので堆肥の施用は敬遠されがちであり、輸送コストや投入経費等のコスト的な問題も大きい。これらの問題を解決するためには、流通や施用に係わる技術開発により低コスト化を図ることも重要である。さらに、商品としての堆肥を売るだけでなく、運搬から散布までを含めた流通システムを構築することが、これから、だぶつくことが予想される堆肥の販路を拡大維持するための賢明なやり方ではないだろうか。また、堆肥の新たな使用方法の作出も需要拡大に必要となる。 耕種サイドとしては、堆肥を投入することによって増えるであろうコストに見合った効果がなければ堆肥を施用しようという機運にはならない。堆肥を使用による効果としては ①有機農産物としての付加価値 ②地力の増進に伴う化学肥料施用量の削減や追肥の省略 ③土づくり効果による作物の安定生産 このなかで、堆肥を施用したにもかかわらず、減肥しないと生産が不安定になったり、環境への負荷が増大する等の悪影響も懸念される。堆肥連用を前提とした施肥基準を策定する等の耕種部門からの取り組みも必要になってくる。 |
各種有機物の特性と施用上の注意
| 有機物の種類 | 原 材 料 | 施 用 効 果 |
施用上の注意 最も安心して施用できる |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肥料的 |
化学性 改 良 |
物理性 改 良 |
||||
| 堆 肥 |
稲わら、麦かん、野菜くず など |
中 | 小 | 中 |
肥料的効果を考えて施用量を 決定する |
|
| 厩 肥 | (牛 糞 尿) | 牛糞尿と敷料 | 中 | 中 | 中 |
未熟木質があると虫害が発生 しやすい |
| (豚 糞 尿) | 豚糞尿と敷料 | 大 | 大 | 小 | ||
| (鶏 糞 尿) | 鶏糞とわらなど | 大 | 大 | 小 | ||
|
木質混合 堆 肥 |
(牛 糞 尿) | 牛糞尿とおがくず | 中 | 中 | 大 |
未熟木質があると虫害が発生 しやすい |
| (豚 糞 尿) | 牛豚糞尿とおがくず | 中 | 中 | 大 | ||
| (鶏 糞 尿) | 鶏糞尿とおがくず | 中 | 中 | 中 | ||
| バーク堆肥 |
バークやおがくずを主体に したもの |
小 | 小 | 大 |
物理性の改良効果を中心に 考える |
|
| 籾がら堆肥 | 籾がらを主体にしたもの | 小 | 小 | 大 | ||
| 都市ごみコンポスト | 家庭のちゅう介類など | 中 | 中 | 中 | ガラス等の異物混合に注意 | |
| 下水汚泥堆積物 | 下水汚泥及び水分調整剤 | 大 | 大 | 小 | 石灰の量に注意 | |
| 食品産業廃棄物 | 食品産業廃棄物水分調整剤 | 大 | 中 | 小 |
肥料的効果を考え施用量を 決定 |
|
| 農業技術体系(藤原、1986) | ||||||
